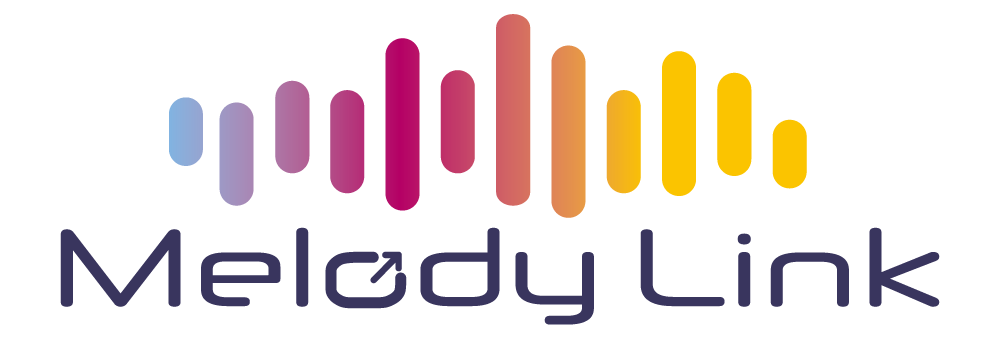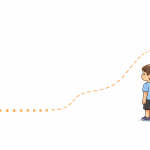世の中には「みんながやっていることに合わせる」ほうが安心だ、という空気があります。
確かにそれは安全な選択ですし、悪くはありません。
でも、多くの人が同じ方向を向いて動いていると、その中で自分が埋もれてしまうこともあります。
一方で、ほんの少し視点をずらして“逆張り”で動くと、自分だけのポジションやチャンスが見つかることがあります。
これは仕事でも趣味でも、どんな分野でも共通して言えることです。
パレートの法則と2:6:2の分布
「パレートの法則」や「2:6:2の法則」という考え方があります。これは、人や成果の分布が大きく三つに分かれるというものです。
- 上位2割:突出した成果を出す人たち
- 中間6割:平均的な成果を出す人たち
- 下位2割:成果が低い人たち
この割合は、ビジネスでも芸術でも、意外といろんな場面で見られます。
「6」を狙うとどうなるか
安全にいくなら、真ん中の「6」を狙うのが一番リスクは低いです。
大きく外すことはないけれど、大きく当たることも少ない。
もちろん、いわゆる“持ってる”タイプの人は、そこを狙っても不思議と上手くいくことがあります。
でも僕はそうじゃなくて、「よし、この平均を取ろう!」と狙いにいくと、なぜかそのちょっと下の結果になることが多いんです。
狙い目は「4」=逆張りゾーン
だから僕はあえて「4」を狙うようにしています。
これは中間から少し外れた位置で、周囲からは奇抜に見えるかもしれません。
でも逆張りで動くと、競合が少なく、自分だけの表現を確立できるチャンスが生まれます。
勝負がハマったときのリターンも大きいのが魅力です。
例え:フェスで選んだ“空いてる店”
例えば、とあるフェスで飲食ブースに行ったとき。
ハンバーガーやケバブのような人気メニューはどこも長蛇の列でしたが、アルゼンチン料理のブースは比較的空いていました。
「ここでしか食べる機会はないかも」と思って選んでみたら、初めての味に出会えて、とても美味しかったんです。
多くの人が並ぶ列に加わらず、空いているお店を選んだからこそ得られた新しい体験。
こうした小さな出来事も、逆張りの価値を象徴していると思います。
逆張りを“無謀”で終わらせないための対策
話を本題に戻すと、何の準備もなく逆張りすると失敗率は高くなります。
大事なのは、失敗しても致命傷にならないようなリスクヘッジをしておくこと。
プランBや撤退ラインをあらかじめ決めておくと、思い切った挑戦がしやすくなります。
その状態で動けば、成功する確率はぐっと上がります。
失敗は悪じゃない
ここで僕が強く思っているのは、「失敗は悪じゃない」ということです。
もちろん、リスクヘッジは必要です。無防備に挑戦するのは違う。
でも、ちゃんと備えをしていれば、失敗も次に繋がる経験になるし、むしろ得られるものは多いと思うんです。
挑戦の中で得た気づきやスキル、人との繋がりは、数字では測れない財産。
僕はむしろ、それこそが“逆張りの価値”なんじゃないかとも思います。
選択はあなた次第
音楽でも、ビジネスでも、あるいは日常の小さな挑戦でも──少し外れた逆張りの道には、必ず新しい経験や厚みが積み重なります。
だから僕は、面白い人生を作りたいなら“4”を選ぶ価値があると思っています。
6を選んで安心するか、4を選んでワクワクするか──その選択は、やっぱりあなた次第です。